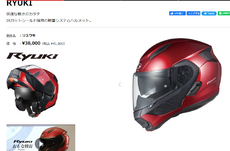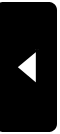2018年08月20日
亀の子ボックスまとめ
※次男との西浜キャンプ場は加筆しました。
連休前の記事にこのようなコメントを頂きました。
「初めて投稿させていただきます。1400gtr 乗りですが、亀の子が気になっています。どこのホムセン箱をどのように設置していますでしょうか?過去記事を追っておりますが見つけられていません。設置の詳細記事などすでに投稿されていらっしゃればその記事を教えていただければと思います。よろしくお願い致します。」
おお、亀の子BOXに食らいつく奇特な方が現れました。
確かに亀の子ボックス限定で投稿した記事がありませんでしたな。リクエストに応えようと過去記事を検索するとタイトルと亀の子の繋がりが無い物ばかり。かなり苦戦しました。
とりあえず、作成方法とバイクへの取り付け方に分けてまとめてみます。
亀の子1号(下600上450F)

亀の子2号(下800上600F)

1. 概要
メーカー:アイリスオーヤマ https://www.irisplaza.co.jp/index.php?KB=KAISO&CID=4248
商品名:RVBOX600/800/450F/600F
メーカーHPかこの記事で確認できます。
構 造:下の親亀のフタに子亀をボルトオンするだけ
ホムセンで売っているタイダウンベルト200~400円くらいのをボルトオン
取付方法:バイクに合わせてパイルダーオン!
2. 作成方法
親亀(下)のフタに子亀本体を固定する方法はこの記事の中盤辺りから確認できます。
子亀のフタ塗装とフタ飛ばし防止についてはこの記事
親子合体の注意点は、4ヶ所の穴位置です。親蓋裏の補強板に重なるとナットが干渉するので板を削らなければなりません。私は飲みながらやるので繊細なことはしません。干渉した板を削りました。
固定したナットの頭は防水処理のためボンドをたっぷりかぶせました。未だ大雨の中走っても浸水はありません。
子亀の蓋は後ろから開ける方が蓋飛びの心配がありません。私は使い勝手を優先し前開けにしてます。今はゴムバンドをかけて防止してます。
3. バイクへの取り付け
最初に下のボックスに荷締めベルトを取り付けます。ホムセンで200円くらい。取り付け金具は「カチオン電着塗装・曲板黒・M6」。この板でボックス本体を外と中から挟むようにして強度を高めます。亀の子じゃありませんが、この記事で確認できます。
このベルトの取り付け方にはメリットがあって、必要のないときはベルトを箱の内部に仕舞えることです。
続いてバイクへの固定の仕方ですが、1400GTRの場合。シートに直載せはできません。斜めになるし、何と言ってもパニアケースの取り外しが箱と干渉してできなくなります。そのために高さを稼ぐ自作パット?と車用で腰痛防止用の腰パットを流用しています。この腰痛防止パットの角度がちょうど良いのですよ。部材は100均です。そのあたりの記事の中盤から書いてあります。
※記事ではマットを6枚重ねにしていますが、これはクロスカブ用。GTR要は3~4枚を重ねたものを使用しています。シートの上にさかさまにした腰痛マット、その上に100均パット、そしてボックスとなります。選択したボックスのサイズに応じて調整してみてください。腰痛マットを使用したのはたまたまそこにあったからです。
続いてバイクへの固定方法はこちら。
箱に直付けしたバンドで4点留め。今年から前側も逆Y字型に留めました。ずれ防止のためです。腰痛マットが意外な点でメリットになります。それはトップケースを併用した場合、その蓋の開閉時に亀の子と干渉します。しかし、亀の子を前に押してやるとマットなので多少傾くんですよね。それで開閉のクリアランスを確保してます。とは言っても全開には出来ませんけどね。
補足の写真




蓋を閉めるときは押し込みます。

まとめ
亀の子サイズ決めは持っていくツールの最大幅を基準にした方が良いです。600(1号)から800(2号)に変更したのはヘリノックスのコットが600には収まらず、サイドパニアにも入らなかったためです。
子亀の使い勝手は保証します。グローブボックス的な用途。飲み物、地図、モバイルバッテリーによる充電、買い物入れ、ソフト保冷ボックス、100均ボトルに入れた雑巾なんかも。降りた時のグローブやサングラスなんかも入れています。雨が降り出した時はウエストパックをそのまま収納できます。
バイクへの固定はトップケース、サイドパニアとの干渉回避が重要だと思います。地合わせで試してみてください。
時間があればもう少し詳しく作り直したかったんですが、これでご勘弁を。質問があれば遠慮なくコメント欄でお願いします。
同じ1400GTR乗りとして、どこかでお会いできると良いですねぇ!
以上。
ポチっとして頂けたら張り合いが出ます。すぐにバックしていただいてかまいません。

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村
連休前の記事にこのようなコメントを頂きました。
「初めて投稿させていただきます。1400gtr 乗りですが、亀の子が気になっています。どこのホムセン箱をどのように設置していますでしょうか?過去記事を追っておりますが見つけられていません。設置の詳細記事などすでに投稿されていらっしゃればその記事を教えていただければと思います。よろしくお願い致します。」
おお、亀の子BOXに食らいつく奇特な方が現れました。
確かに亀の子ボックス限定で投稿した記事がありませんでしたな。リクエストに応えようと過去記事を検索するとタイトルと亀の子の繋がりが無い物ばかり。かなり苦戦しました。
とりあえず、作成方法とバイクへの取り付け方に分けてまとめてみます。
亀の子1号(下600上450F)
亀の子2号(下800上600F)
1. 概要
メーカー:アイリスオーヤマ https://www.irisplaza.co.jp/index.php?KB=KAISO&CID=4248
商品名:RVBOX600/800/450F/600F
メーカーHPかこの記事で確認できます。
構 造:下の親亀のフタに子亀をボルトオンするだけ
ホムセンで売っているタイダウンベルト200~400円くらいのをボルトオン
取付方法:バイクに合わせてパイルダーオン!
2. 作成方法
親亀(下)のフタに子亀本体を固定する方法はこの記事の中盤辺りから確認できます。
子亀のフタ塗装とフタ飛ばし防止についてはこの記事
親子合体の注意点は、4ヶ所の穴位置です。親蓋裏の補強板に重なるとナットが干渉するので板を削らなければなりません。私は飲みながらやるので繊細なことはしません。干渉した板を削りました。
固定したナットの頭は防水処理のためボンドをたっぷりかぶせました。未だ大雨の中走っても浸水はありません。
子亀の蓋は後ろから開ける方が蓋飛びの心配がありません。私は使い勝手を優先し前開けにしてます。今はゴムバンドをかけて防止してます。
3. バイクへの取り付け
最初に下のボックスに荷締めベルトを取り付けます。ホムセンで200円くらい。取り付け金具は「カチオン電着塗装・曲板黒・M6」。この板でボックス本体を外と中から挟むようにして強度を高めます。亀の子じゃありませんが、この記事で確認できます。
このベルトの取り付け方にはメリットがあって、必要のないときはベルトを箱の内部に仕舞えることです。
続いてバイクへの固定の仕方ですが、1400GTRの場合。シートに直載せはできません。斜めになるし、何と言ってもパニアケースの取り外しが箱と干渉してできなくなります。そのために高さを稼ぐ自作パット?と車用で腰痛防止用の腰パットを流用しています。この腰痛防止パットの角度がちょうど良いのですよ。部材は100均です。そのあたりの記事の中盤から書いてあります。
※記事ではマットを6枚重ねにしていますが、これはクロスカブ用。GTR要は3~4枚を重ねたものを使用しています。シートの上にさかさまにした腰痛マット、その上に100均パット、そしてボックスとなります。選択したボックスのサイズに応じて調整してみてください。腰痛マットを使用したのはたまたまそこにあったからです。
続いてバイクへの固定方法はこちら。
箱に直付けしたバンドで4点留め。今年から前側も逆Y字型に留めました。ずれ防止のためです。腰痛マットが意外な点でメリットになります。それはトップケースを併用した場合、その蓋の開閉時に亀の子と干渉します。しかし、亀の子を前に押してやるとマットなので多少傾くんですよね。それで開閉のクリアランスを確保してます。とは言っても全開には出来ませんけどね。
補足の写真
蓋を閉めるときは押し込みます。
まとめ
亀の子サイズ決めは持っていくツールの最大幅を基準にした方が良いです。600(1号)から800(2号)に変更したのはヘリノックスのコットが600には収まらず、サイドパニアにも入らなかったためです。
子亀の使い勝手は保証します。グローブボックス的な用途。飲み物、地図、モバイルバッテリーによる充電、買い物入れ、ソフト保冷ボックス、100均ボトルに入れた雑巾なんかも。降りた時のグローブやサングラスなんかも入れています。雨が降り出した時はウエストパックをそのまま収納できます。
バイクへの固定はトップケース、サイドパニアとの干渉回避が重要だと思います。地合わせで試してみてください。
時間があればもう少し詳しく作り直したかったんですが、これでご勘弁を。質問があれば遠慮なくコメント欄でお願いします。
同じ1400GTR乗りとして、どこかでお会いできると良いですねぇ!
以上。
ポチっとして頂けたら張り合いが出ます。すぐにバックしていただいてかまいません。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
※会員のみコメントを受け付けております、ログインが必要です。